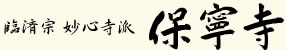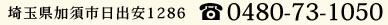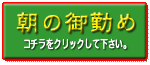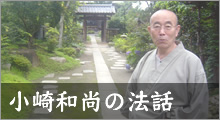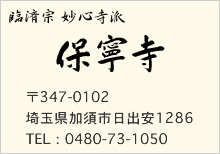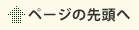保寧寺(ほねいじ)は埼玉県加須市日出安にある臨済宗妙心寺派の寺院です。
開山は鎌倉時代末期と言われており、歴史あるお寺です。
ホームページでは保寧寺の見所をご案内いたしますので、どうぞご参拝の際の参考にしてください。
保寧寺の活動としては座禅会や写経会、仏教講座や御詠歌の会などを行っています。
埼玉県の寺院で座禅会や写経会をお探しのかたは、お気軽にご参加ください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
◎下のボタンをクリックすると、勤行のページに移動します。
朝の御勤めにお役立て下さい。
改暦の嘉義、誠にめでたく謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
師走に眺めた月も新年に眺める月も然したる変わりがある訳でもありませんが、物みな新た、と古人も言ってもおります。一年一年をくぎって身も心も新たな様相で再出発というか軌道修正の時を得て、未来に向かって漕ぎ行く年年歳歳はまことに潔いものです。
「松に古今の色無く 竹に上下の節有り」と言った有名な禅語などもあって普遍の真理も平等と差別の共有があって構成されているのです。因みにこの禅語には「梅自ずから発いて清香あり」の句が続いて、松 竹 梅の目出度さも謳っています。干支(えと)の動物は中国が起源ではありますが、それぞれにそれらしい目出度さにあやかる意味を持っておりますが、今年の馬も新年に願うべき目出度さをひっさげての登場です。馬には、活発、積極、行動力に富んでいる、また、熱意と寛大さをもって人々と接する為にも積極的動くといった性格付けがあり、勇ましい年になるやも知れませんねえ。
皆様の菩提寺、保寧寺の地、騎西はなんとどっこい、馬ととても深い因縁で繋がっているのですが、ご存知ですか?
騎西町に有る玉敷神社の無病息災を祈る「お馬くぐり」という神事や戦国時代に騎西城跡から出土した馬甲などからも「騎西」と馬とが結びついた馬信仰の深い処であったのです。「騎西」の騎は馬に乗るという意味ですね。そういう訳でこの騎西の地は戦国時代には名馬の生産地として軍事的にも深く関わっていたのです。保寧寺の近くに駒形神社がありますが、「源平盛衰記」や「平家物語」等にも騎西馬を褒め上げた件があります。騎西と保寧寺にご縁があります皆さんにとってより一層の良き年であることを願ってやみません。
小崎無一 九拝
和尚のつぶやき / お知らせ
- 2024年6月27日
- 巡礼 旅の終わり
- 2024年6月18日
- 巡礼 ガウデイ責め
- 2024年6月18日
- 巡礼 サクラダファミリア 地下お御堂
- 2024年6月18日
- 巡礼 サンタ マリア デル コロ
- 2024年6月17日
- 巡礼 サンテリヤーナ デル マル
- 2024年6月16日
- 巡礼 騙されました
- 2024年6月16日
- 巡礼 鍵
- 2024年6月16日
- 巡礼 ゲルニカのゲルニカ